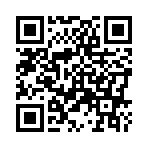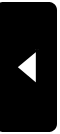2017年10月10日
酒田でオーラルフィジシャン・チームミーティング
入れ歯に頼ることなく生涯にわたって自分の歯で過ごせるよう、口の中の健康を守ることを目的にしている全国の歯科医療従事者が一堂に会する「オーラルフィジシャン・チームミーティング」が7日、酒田市の希望ホールで開幕。国内外から招いた講師の講演などを通して8日(日)までの2日間、全国各地から集った従事者たちが歯科医療の目指すべき姿をあらためて考察する。
オーラルフィジシャンは、虫歯や歯周病を発生させないよう、口腔(こうくう)の健康を総合的に管理する歯科医師のこと。このミーティングは、世界標準の歯科医療の構築と実践などを目的に、同市の日吉歯科診療所(熊谷崇院長)が開いている「オーラルフィジシャン育成セミナー」を修了した歯科医院スタッフが集まり、2006年から毎年この時期に開催。年々規模が拡大しており、今年は北海道から九州まで全国各地から従事者約800人が参加した。 歯科口腔内カメラ
初日の7日午前は、丸山至酒田市長が「歯と口腔の健康維持に向けた先導的な役割を担っているのが熊谷先生。市では昨年、『歯と口腔の健康づくり推進条例』を制定しており、歯の健康日本一を目指している。地域の行政を巻き込み、これからも歯の健康を考えて活動を展開してください」と歓迎あいさつし幕開け。引き続き「歯科医療の未来―世界の歯科事情を通して」の主テーマで、タイ、英国、日本の歯科医療を取り巻く現状に関して識者7人が登壇した。
このうち「KEEP28達成のための医と産業の新しい連携『ここで始めることが世界を変える』」と題し語った熊谷院長は、生涯にわたり全ての歯を守る「KEEP28」について「生涯にわたって口腔内の健康を維持するという『価値』を患者と共有しなければいけない」と話し、実現に向けた手段として▽専門医との連携▽科学的根拠に基づいた治療▽メンテナンス▽クラウドによる情報提供―を挙げた。 歯科インプラント
さらに、提供した歯科医療のアウトカム(本質的な成果)の評価を検証することの大切さを説いた上で現在、口腔の健康状況を患者に広く情報提供するため電気大手・富士通と共に取り組んでいる「クラウドサービス」について語った。
2日目は、13年に日経WOMAN「ウーマン・オブ・ザ・イヤー」を受賞した資生堂顧問の関根近子さん(酒田ふるさと観光大使)、ANA総合研究所代表取締役副社長の河本宏子さんの講演、「口腔と全身の関係」と題した3つの講話などが行われる。
http://cogoole.jp/searches/blog_detail/637/46778
オーラルフィジシャンは、虫歯や歯周病を発生させないよう、口腔(こうくう)の健康を総合的に管理する歯科医師のこと。このミーティングは、世界標準の歯科医療の構築と実践などを目的に、同市の日吉歯科診療所(熊谷崇院長)が開いている「オーラルフィジシャン育成セミナー」を修了した歯科医院スタッフが集まり、2006年から毎年この時期に開催。年々規模が拡大しており、今年は北海道から九州まで全国各地から従事者約800人が参加した。 歯科口腔内カメラ
初日の7日午前は、丸山至酒田市長が「歯と口腔の健康維持に向けた先導的な役割を担っているのが熊谷先生。市では昨年、『歯と口腔の健康づくり推進条例』を制定しており、歯の健康日本一を目指している。地域の行政を巻き込み、これからも歯の健康を考えて活動を展開してください」と歓迎あいさつし幕開け。引き続き「歯科医療の未来―世界の歯科事情を通して」の主テーマで、タイ、英国、日本の歯科医療を取り巻く現状に関して識者7人が登壇した。
このうち「KEEP28達成のための医と産業の新しい連携『ここで始めることが世界を変える』」と題し語った熊谷院長は、生涯にわたり全ての歯を守る「KEEP28」について「生涯にわたって口腔内の健康を維持するという『価値』を患者と共有しなければいけない」と話し、実現に向けた手段として▽専門医との連携▽科学的根拠に基づいた治療▽メンテナンス▽クラウドによる情報提供―を挙げた。 歯科インプラント
さらに、提供した歯科医療のアウトカム(本質的な成果)の評価を検証することの大切さを説いた上で現在、口腔の健康状況を患者に広く情報提供するため電気大手・富士通と共に取り組んでいる「クラウドサービス」について語った。
2日目は、13年に日経WOMAN「ウーマン・オブ・ザ・イヤー」を受賞した資生堂顧問の関根近子さん(酒田ふるさと観光大使)、ANA総合研究所代表取締役副社長の河本宏子さんの講演、「口腔と全身の関係」と題した3つの講話などが行われる。
http://cogoole.jp/searches/blog_detail/637/46778
Posted by 歯科技工用遠心鋳造器 at
19:11
│Comments(0)
2017年10月06日
楽しく健康づくり 大岡で「南なんデー」
南区健康福祉まつり「いきいきふれあい南(なん)なんデー」が10月1日、大岡健康プラザで行われた。主催は南区医師会らによる実行委員会(池田嘉宏委員長=南区医師会会長)で26回目。歯科用 セメント
開会セレモニーでは、南区オリジナルの「みなっち体操」があり、参加者が体を動かした。led光照射器
会場には健康や福祉に関する団体がブースを設け、健康や医療についての情報を提供。医師や歯科医師、薬剤師が相談を受け付けるコーナーは開始から順番待ちの列が続いた。南区医師会の4人の開業医がリレー形式で行った講演会では、認知症や在宅医療について語られた。
同医師会は認知症予防に役立てるための「もの忘れチェック」を初めて実施。タブレット端末を使い、表示された単語を思い出すテストや図形認識力などを確かめた。このコーナーを担当した北浜正医師は「手軽にできるものなので、今後もさまざまな場所でチェックを行い、認知症予防につなげたい」と話した。
http://dentaljp.blogspot.com/2017/10/blog-post_4.html
開会セレモニーでは、南区オリジナルの「みなっち体操」があり、参加者が体を動かした。led光照射器
会場には健康や福祉に関する団体がブースを設け、健康や医療についての情報を提供。医師や歯科医師、薬剤師が相談を受け付けるコーナーは開始から順番待ちの列が続いた。南区医師会の4人の開業医がリレー形式で行った講演会では、認知症や在宅医療について語られた。
同医師会は認知症予防に役立てるための「もの忘れチェック」を初めて実施。タブレット端末を使い、表示された単語を思い出すテストや図形認識力などを確かめた。このコーナーを担当した北浜正医師は「手軽にできるものなので、今後もさまざまな場所でチェックを行い、認知症予防につなげたい」と話した。
http://dentaljp.blogspot.com/2017/10/blog-post_4.html
Posted by 歯科技工用遠心鋳造器 at
17:45
│Comments(0)
2017年10月05日
糖質とカルシウムの摂りすぎで歯周病を悪化
そんな歯周病の改善に役立つと考えられている食品がある。それは「海藻」だ。歯周病と食生活の関連に詳しく、『名医は虫歯を削らない――虫歯も歯周病も「自然治癒力」で治す方法』(竹書房)の著書を持つ小峰歯科医院の小峰一雄院長は、その理由について次のように語る。歯科口腔内カメラ
「日々の食生活が歯周病に及ぼす影響は大きい。重要なポイントは、糖質とカルシウムを摂りすぎないこと。マグネシウムを積極的に摂ること。マグネシウムの宝庫で、糖の吸収を妨げる食物繊維も多い海藻は、歯周病防止に有用な食品」 歯科インプラント
糖質は口の中にいる細菌のエサになり、歯垢の元になる。歯垢を放置すると、唾液に含まれるカルシウムなどと結合し、石灰化する。これが「歯石」で、歯石がついた歯ぐきの中は菌の温床となり、歯周病がさらに進行していく。
また、糖質を摂りすぎると、余った糖質がレプチンというホルモンによって脂肪細胞に蓄えられる。この脂肪細胞が巨大化すると、そこから炎症を起こす物質(サイトカイン)が分泌され、歯ぐきに炎症を起こす。
一方、カルシウムは、一般に歯に必要な栄養素とされているが、摂りすぎはかえってよくないという。小峰院長は特に、カルシウムとマグネシウムの摂取バランスが重要と説く。
「マグネシウムは、歯周病を引き起こすカルシウムの循環不良を改善する役割がある。日本ではカルシウム摂取ばかりが強調されるが、海外では30歳以降はマグネシウムの摂取が推奨されている」(小峰院長)
http://athenadental.exblog.jp/25798704/
「日々の食生活が歯周病に及ぼす影響は大きい。重要なポイントは、糖質とカルシウムを摂りすぎないこと。マグネシウムを積極的に摂ること。マグネシウムの宝庫で、糖の吸収を妨げる食物繊維も多い海藻は、歯周病防止に有用な食品」 歯科インプラント
糖質は口の中にいる細菌のエサになり、歯垢の元になる。歯垢を放置すると、唾液に含まれるカルシウムなどと結合し、石灰化する。これが「歯石」で、歯石がついた歯ぐきの中は菌の温床となり、歯周病がさらに進行していく。
また、糖質を摂りすぎると、余った糖質がレプチンというホルモンによって脂肪細胞に蓄えられる。この脂肪細胞が巨大化すると、そこから炎症を起こす物質(サイトカイン)が分泌され、歯ぐきに炎症を起こす。
一方、カルシウムは、一般に歯に必要な栄養素とされているが、摂りすぎはかえってよくないという。小峰院長は特に、カルシウムとマグネシウムの摂取バランスが重要と説く。
「マグネシウムは、歯周病を引き起こすカルシウムの循環不良を改善する役割がある。日本ではカルシウム摂取ばかりが強調されるが、海外では30歳以降はマグネシウムの摂取が推奨されている」(小峰院長)
http://athenadental.exblog.jp/25798704/
Posted by 歯科技工用遠心鋳造器 at
14:44
│Comments(0)
2017年10月03日
歯の寿命は先進国でも最低クラス! 日本で軽視される予防歯科の“やってられない”現実と歯科衛生士不足
埼玉県富士見市にある『医療法人満月会 大月デンタルケア』が他の歯科医院と違うのは、歯を削る治療より、歯を削らずに保存する予防を軸にしている点にある(前回記事参照)。歯科口腔内カメラ
予防歯科の重要性は国も認めていて、厚生労働省は『80歳になっても20本以上の歯を保つ』ことを目指す“8020運動”を1989年から続けている。人間の歯の本数は30本、親知らずを除けば28本だが、厚労省は入れ歯ナシにほとんどの物を食べられる目安を20本とし、高齢者の口腔ケアを推進してきた。歯科インプラント
では、約30年を経た今、“8020運動”の効果は出ているのか? 大月デンタルケアの大月晃院長がこう話す。
「全く効果が出ていないというわけではありませんが、日本では80歳以上の人の約半数が総入れ歯です。予防歯科の先進国・スウェーデンでは80歳以上の方の歯の欠損は平均3本程度。日本は歯の寿命という点でいえば、先進国でも最低クラスです」
前回、詳しく伝えたところだが、日本はコンビニの数より歯科医院の数のほうが多い国だ。歯医者が多ければ国民の歯の寿命は伸びそうなものだが…?
「日本では削る、詰める、抜く…治療型の歯科医院が大半で、医師も患者もそれが当然と思っています。しかし、その治療は応急処置でしかなく、歯を削ればそこにできた段差にむし歯ができやすくなる傾向もあり、根本的な治療にはなりません」
一方、他の先進国では予防型の歯科医療が主流になっているのだという。
http://athenadental.exblog.jp/25790227/
予防歯科の重要性は国も認めていて、厚生労働省は『80歳になっても20本以上の歯を保つ』ことを目指す“8020運動”を1989年から続けている。人間の歯の本数は30本、親知らずを除けば28本だが、厚労省は入れ歯ナシにほとんどの物を食べられる目安を20本とし、高齢者の口腔ケアを推進してきた。歯科インプラント
では、約30年を経た今、“8020運動”の効果は出ているのか? 大月デンタルケアの大月晃院長がこう話す。
「全く効果が出ていないというわけではありませんが、日本では80歳以上の人の約半数が総入れ歯です。予防歯科の先進国・スウェーデンでは80歳以上の方の歯の欠損は平均3本程度。日本は歯の寿命という点でいえば、先進国でも最低クラスです」
前回、詳しく伝えたところだが、日本はコンビニの数より歯科医院の数のほうが多い国だ。歯医者が多ければ国民の歯の寿命は伸びそうなものだが…?
「日本では削る、詰める、抜く…治療型の歯科医院が大半で、医師も患者もそれが当然と思っています。しかし、その治療は応急処置でしかなく、歯を削ればそこにできた段差にむし歯ができやすくなる傾向もあり、根本的な治療にはなりません」
一方、他の先進国では予防型の歯科医療が主流になっているのだという。
http://athenadental.exblog.jp/25790227/
Posted by 歯科技工用遠心鋳造器 at
12:56
│Comments(0)
2017年10月02日
歯髄が持つ自己治癒力の仕組みを解明 新潟大の研究グループ
新潟大学医歯学総合病院の大倉直人助教らの研究グループは、歯髄(歯の神経)が持つ自己治癒力のメカニズムを解明した。歯髄の治癒時に発生する生体内物質をコントロールすることで、より早い虫歯の治癒を促せる可能性があることが分かった。大倉助教は「歯髄の自然治癒力を生かした『削らない虫歯治療』の開発への扉を開けたと考えている」と話している。歯科口腔内カメラ
研究の成果は英国の科学雑誌「サイエンティフィック・リポーツ」に発表した。歯髄の傷の治癒期に、炎症や痛みに関与する生体内物質プロスタグランジンE2が発生するが、これまで未解明だったその輸送経路と新たな役割を、世界で初めて明らかにしたという。歯科インプラント
虫歯は進行すると歯の内部組織である歯髄に波及し炎症や痛みを生じる。これまでの治療では、歯髄を除去するために歯を削ったが、物理的に歯をぜい弱化させ、将来的に歯を失うリスクが高まることが課題の一つとされてきた。
大倉助教と新潟大大学院医歯学総合研究科の野杁由一郎教授らは、ラットの動物実験で、虫歯などが原因で歯髄が炎症状態になったときに発生するプロスタグランジンE2について解析した。
その結果、歯髄組織内で産出されたプロスタグランジンE2が、プロスタグランジントランスポーター(PGT)と呼ばれる輸送タンパクによって細胞の外に運ばれ、象牙芽細胞や神経、血管にある受容体(EP2)と結合することで、歯の象牙質の修復や神経保護、血管の新生に大きく寄与していることを突き止めた。
大倉助教は「今後は研究の成果を臨床につなぎ、人が持つ回復力や修復力、保護力を生かした、新しい治療法の開発を目指していきたい」と話した。
http://athenadental.exblog.jp/25752180/
研究の成果は英国の科学雑誌「サイエンティフィック・リポーツ」に発表した。歯髄の傷の治癒期に、炎症や痛みに関与する生体内物質プロスタグランジンE2が発生するが、これまで未解明だったその輸送経路と新たな役割を、世界で初めて明らかにしたという。歯科インプラント
虫歯は進行すると歯の内部組織である歯髄に波及し炎症や痛みを生じる。これまでの治療では、歯髄を除去するために歯を削ったが、物理的に歯をぜい弱化させ、将来的に歯を失うリスクが高まることが課題の一つとされてきた。
大倉助教と新潟大大学院医歯学総合研究科の野杁由一郎教授らは、ラットの動物実験で、虫歯などが原因で歯髄が炎症状態になったときに発生するプロスタグランジンE2について解析した。
その結果、歯髄組織内で産出されたプロスタグランジンE2が、プロスタグランジントランスポーター(PGT)と呼ばれる輸送タンパクによって細胞の外に運ばれ、象牙芽細胞や神経、血管にある受容体(EP2)と結合することで、歯の象牙質の修復や神経保護、血管の新生に大きく寄与していることを突き止めた。
大倉助教は「今後は研究の成果を臨床につなぎ、人が持つ回復力や修復力、保護力を生かした、新しい治療法の開発を目指していきたい」と話した。
http://athenadental.exblog.jp/25752180/
Posted by 歯科技工用遠心鋳造器 at
15:58
│Comments(0)